書評『インバウンドマーケティング―オンラインで顧客を惹きつけ、招き、喜ばせるマーケティング戦略』Halligan,Brian Shah,Dharmesh 著/前田健二 翻訳
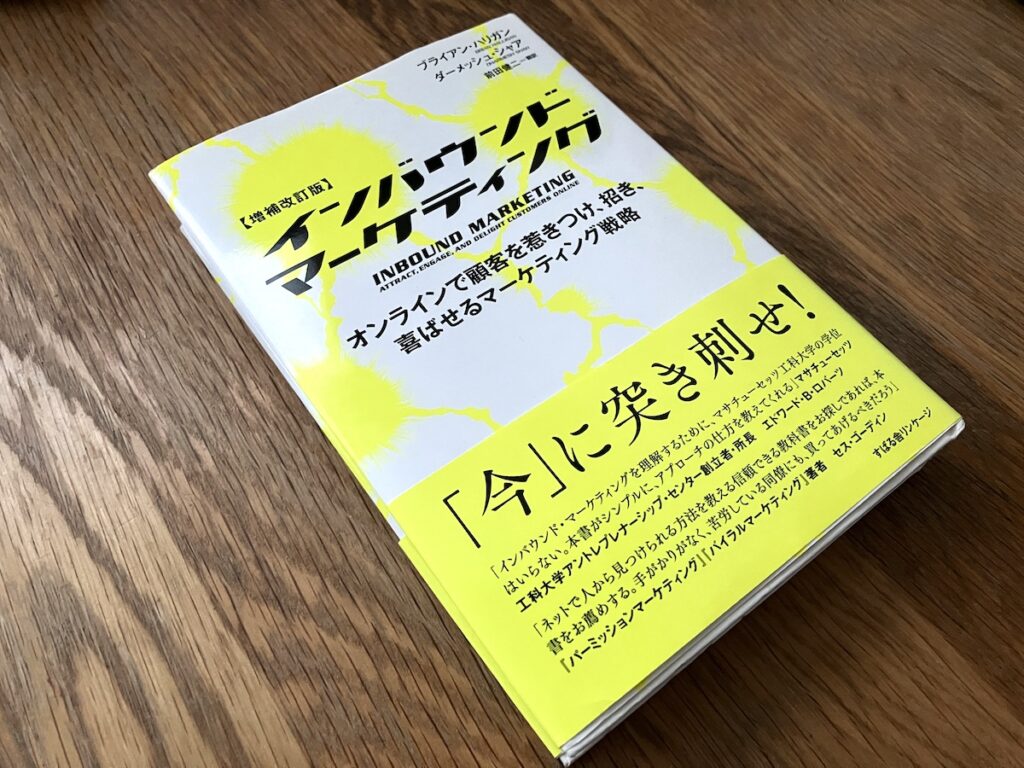
インバウンドマーケティングをこれまでにやったことがない方に向けた実践的な書籍です。比較的基礎的なことが書かれていますが、自分にとってまだまだ勉強になる部分が多い印象を持ちました。また、既知の基礎的な施策も徹底的にできてるかと言われると自信を持ってYESとはいえないと反省しました。
施策に行き詰まった時に読み返してみると、現状を打破するためのヒントが見つかりそうな書籍です。
今回のブログでは、新たな気づきを得たり、勉強になったりした部分を引用しつつまとめました。
新たな気づきを得たり、勉強になったりした点
| サイトの訪問者には、あなたのウェブサイトは適切に見え、そこでどんなカラーやメニューが使われていようと別段気にしない。訪問者は、自分にとって興味が持てる「何か」を求めて訪問しているに過ぎない。 『インバウンドマーケティング―オンラインで顧客を惹きつけ、招き、喜ばせるマーケティング戦略』 |
ユーザーが求めているのは自分の課題を解決してくれる情報なので、ウェブサイトでこだわりを持つべきポイントは、情報が伝わるようになっているかという点。デザインは二の次。
商材によってどこまでデザインにこだわるか変わってきますが、最低限の体裁やウェブサイトの雰囲気づくりのためのデザインができていればOKとして、コンテンツに時間をかけることにリソースを投下したいですね。
| まず知っておくべきことは、あなたのウェブサイトの現時点での登録者数だ。ここで言う登録者数とは、あなたのウェブサイトのRSS登録者とメールマガジンの登録者と定義しておこう。さらに、Facebook、リンクトイン、ツイッター等のソーシャルメディアでのあなたのフォロワー数も登録者に加えておこう。 『インバウンドマーケティング―オンラインで顧客を惹きつけ、招き、喜ばせるマーケティング戦略』 |
これまで私は、「ウェブサイトをどのように改善するか」という考えが強く、他のメディアでの戦略はあまり考えられていませんでした。
ウェブサイトの改善はもちろん重要ですが、他のメディアも利用する視点は持ってていなかった点は私自身の改善ポイントです。
これからは、エンドクライアントがどこでどんなメディアに接することが多いのかの分析も行いたいと思います。
また、先日とあるP-MAXに関するセミナーに参加して、カスタマージャーニーの複雑性によってもP-MAXの有効性は変わってくるかもしれないということを学びました。
P-MAXを効果的に運用するためにも、ユーザーの行動に思いをめぐらせることに力を入れていきたいと思います。
| あなたはもはや、大金をはたいて見込み客に押し売りをする必要はない。突き抜けたコンテンツを作り上げ、サーチエンジンとソーシャルメディアにのせ、公開し、ブログやソーシャルメディアを使って伝播させ、一連の効果を測定すればいい。 『インバウンドマーケティング―オンラインで顧客を惹きつけ、招き、喜ばせるマーケティング戦略』 |
クライアントの支援の際に、SEO対策としてのコンテンツ作成と捉えていたため、サーチエンジンに乗せるという視点しかありませんでした。
最近では、Xが公式に外部リンクを貼る際のポイントを発信したこともあり、ソーシャルメディアに乗せる際の一工夫も必要になっていますので、その辺りのキャッチアップも行いつつ、ソーシャルメディアでの拡散も狙っていかないとなと思います。
また、コンテンツの品質の評価基準として、労力(Effort)、独自性(Originality)、才能や技術(Talent or Skill)があることを踏まえると、読み手の意図や感情に寄り添って、課題の解決を助けてあげるコンテンツを作る。課題解決方法は生成AIが教えてくれるけど、読み手の意図や感情は人間が想像した方が正解に近いと思う。そこに人間が労力を払う必要がありそう
| ほとんどの企業が直面する一番の課題は、サイト訪問者を見込み客に変えることではなく、自社サイトへの集客を増やすことである。つまり、改善すべきなのは、この時間配分の問題である。仕事の8割を自社サイトの集客にあて、残りの2割ほどの力でコンバージョンレートの改善に努めるのが、SEO対策の正しい時間配分だ。 『インバウンドマーケティング―オンラインで顧客を惹きつけ、招き、喜ばせるマーケティング戦略』 |
最近の私はコンバージョンを獲得することに目が眩んで、セッション数×コンバージョン率=コンバージョン数という原則を忘れていました。
短期的なコンバージョン獲得を目指すあまり、ページ内部の改善に目が行きがちになっていたと思います。
その結果、広告以外でセッション数を伸ばす施策が打てておらず、中長期でコンバージョン数を伸ばせずに苦しむという構図になっていました。
ページ内部の改善はもちろん大切ですが、SEO対策があまりされていないサイトの場合は、コンバージョン率を上げるよりも、セッション数を伸ばすための施策の方がクライアントの売上へのインパクトが大きいと思います。
コンバージョン率は外部要因に影響を受けて上下しやすい中で、セッション数はちゃんとした方法で上げればそう簡単に下がることがないためです。
広告運用代行をご依頼いただいているクライアントに対して、SEO対策の重要性を認識していただくようにアプローチしていこうと思います。
| どんな見込み顧客とも正面からコンスタントに向き合わないと、彼らとより頻繁に接触しているライバル企業に先を越されてしまうだろう。 『インバウンドマーケティング―オンラインで顧客を惹きつけ、招き、喜ばせるマーケティング戦略』 |
| 見込み客をランク分けし、質の高い見込み客を優先し、質の低い見込み客の育成が重要になる 『インバウンドマーケティング―オンラインで顧客を惹きつけ、招き、喜ばせるマーケティング戦略』 |
ここが一番私ができていなかったなぁと思った点です。
WEBマーケティングに力を入れる企業が増えてきた中で、検索結果画面の戦いは熾烈を極めていると感じます。
特にビッグワードや顕在層の検索クエリでの上位表示は、後発だとかなりの時間がかかりそうです。
そのため、純顕在層の顧客との繋がりを大切にする必要があるのですが、その辺りの施策が何もできていませんでした。
WEBサイトの中で何をするかに終始してしまっていたので、考え方をがらっと変えることが必要です。
その上で、この施策はナーチャリングという考え方ではなく、繋がってくれた方々の役に立ちたいという思いで行うことが大切だとアナグラムさんの動画を見て学びました。
WEBサイトを訪問してくれた方がその場でコンバージョンしなくても、メルマガやLINE、Twitterなどを登録するメリットを訴求して登録を促す。登録してくれた方々が役に立つ情報を発信する。その中で、いざという時に一番に思い出してもらえるようにする。このような設計がとても大切だと学びました。
まとめ
まだまだクライアントのためにできることや勉強しないといけないことは山ほどあると思いました。
マーケティングは、能動的であり続けられる素晴らしい仕事だと思います。